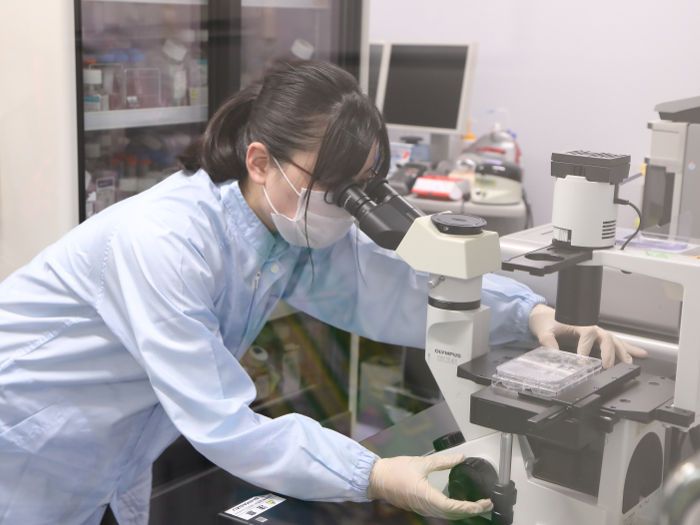2018.11.15
実用化まであと何年?加速するiPS細胞による医療研究
京都大学 iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 幹細胞医学分野 井上治久教授【後編】
山中伸弥氏のノーベル生理学・医学賞受賞で広く知られるようになった「iPS細胞」。京都大学 iPS細胞研究所の井上治久教授へのインタビュー前編では、iPS細胞の医学的価値とその活用法について知ることができたが、果たしてこれからiPS細胞研究はどんな局面を迎えようとしているのだろうか。後編では、iPS細胞を介した難病治療研究の最前線と、その先の未来について迫る。
iPS細胞が特定疾患ALSの治療ターゲットを突き止めた日
前編では、iPS細胞が世界の医学者から期待されている意味や、どのように活用しているのかを語ってくれた井上治久教授。現在は、その方法を駆使し、難病のメカニズムや原因の解明、創薬といった段階にコマを進めている。具体的にどのような研究を行っているのだろうか。
※【前編】の記事はこちら
「難病の一つである筋萎縮性側索硬化症(ALS)でいうと、まずは健康な方からと、遺伝子に変異がある家族性ALS患者さんから、そしてその遺伝子変異を修復したものから、それぞれのiPS細胞を用意して、運動神経細胞へと分化させ、比較しました」
ALSとは、脳や脊髄からの命令を筋肉に伝達する運動神経細胞が正常に機能しなくなる難病。全身の筋肉が動かしにくくなり、病状が進行すると歩行や呼吸をすることも困難になる。病勢の進展も速く、人工呼吸器を使用しなければ通常2~5年で生存できなくなることが多いという。ALS患者の多くは個別に発症する「孤発性ALS」だが、全体の約10%は血縁内で発症例を持つ「家族性ALS」とされる。井上教授は、家族性ALSに注目することで原因となる現象を調べようとしたのだ。

-
井上教授は、培った技術を用いて他の研究者の神経難病研究に協力。これまで「シャルコー・マリー・トゥース病」「脊髄小脳変性症」「近位筋優位遺伝性運動感覚ニューロパチー」など、神経系の病気の研究協力を行ってきたという
「すると、ALS患者さん由来の運動神経細胞だけ、異常に折り畳まれたタンパク質が蓄積し、細胞死を起こすことが分かりました。そこで、他の疾患ですでに用いられている薬剤である、1416種類の化合物を一つ一つ加えてみたのです」
効果を発揮したのは、1416のうち27種類。井上教授は、その27種類の化合物の半数が、特定のタンパク質に対して影響を及ぼしていることを発見したという。
「その特定のタンパク質について詳しく調べてみると、患部細胞が死ぬ原因が、このタンパク質が伝える細胞内の伝達経路にあることが分かりました。これまで多くのALSの原因遺伝子が見出されていましたが、逆にこの研究ではALSの治療のためのターゲットとなる標的分子候補を突き止めることができました」
2017年5月に発表されたこの研究成果。治療標的分子候補が見きわめられたことで、より効果的で全く新しいアプローチによる治療法が確立できる可能性が出てきたわけである。これは100年を超えるALS研究の長い歴史の中でも大きな成果であり、転換点といえるのではないだろうか。
しかし井上教授の試みは、ここで終わらない。この治療標的を抑える薬として、慢性骨髄性白血病、いわゆる白血病に用いられる治療薬ボスチニブを用いて、実験を続けた。
「ALS細胞内部の標的分子を抑制する効果のあるボスチニブを与えてみたのです。すると、細胞内に異常に折り畳まれた異常なタンパク質を減らし、運動神経細胞が死ぬことを抑制しました。しかも家族性ALSだけでなく、孤発性ALS患者さん由来の運動神経細胞でも同様の効果があることも分かったのです」
これは、より多くのALS患者に効果が期待できることを示唆している。その後、ボスチニブの投与は、マウスでの実験へと移行。発症を遅らせ、生存期間を延長する成果が出ているという。iPS細胞を用いた研究によってALS治療研究は現在、ヒトを対象とした臨床試験へ進むための準備段階である。
iPS細胞活用で解明された事実も多い半面、課題も山積み
新たな治療法確立の可能性まで見いだしたALSに対して、井上教授の研究チームが注力しているもう一つの難病、アルツハイマー病の研究はどうだろうか。前編で語ってくれた、脳内でのアミロイドβ(ベータ)という成分のたまり方の違いを発見した後、アミロイドβが神経細胞の外側にたまるタイプのアルツハイマー病のアミロイドβを低減させる方法を模索しているという。
「アルツハイマー病患者さんの多くは、病院に来られたときにはかなり進行していて、その脳内ではおよそ20年前からアミロイドβがたまり続けていると言われています。そのことを考えると、将来の治療には長期間服用して、どのような副作用が生じる可能性があるかなどが判明している安全な薬が求められると考えました」
そこで井上教授は、アルツハイマー病に対して、市販薬の中からアミロイドβを低減させる効果があるものがないか、患者由来のiPS細胞を使って調査した。

-
出来上がった目的の細胞の数を、顕微鏡をのぞきながらカウンターで数えて確認する
「結果から言うと、1200種類以上の既存薬を試しましたが、残念ながら大幅に低減させるものはありませんでした。しかし、そこで諦めるわけにいきませんから、今度はその中でも低減効果があった化合物同士を組み合わせることで、効果を増強させようと試みたのです」
アミロイドβを低減させる市販薬を分子構造が類似している10グループに分類し、中でもアミロイドβ低減効果が強いもの、また与える量が多ければ多いほど効果を発揮するものを選出。6種類の化合物に絞り込んだ。
「その6種類から、2種あるいは3種を組み合わせて新たな化合物を作り、総当たりで比較したのです。すると、パーキンソン病などの薬『ブロモクリプチン』、喘息(ぜんそく)の薬『クロモリン』、抗てんかん薬「トピラマート」の組み合わせが最も効果的であることが分かりました」
一定の成果が認められたものの、井上教授はまだまだ課題も多いと続ける。
「一番大きいのは、アミロイドβを低減させるメカニズムが、まだ明確になっていないということ。新しく作った化合物はアミロイドβを低減させる効果はありましたが、それぞれどの部分に効いているのかが分かりません。治療標的を同定することが、さらにアルツハイマー病への理解を深め、より有効的な治療薬の発見につながる可能性があると考えています」
脳脊髄の難病研究を、複数かつ複合的に行えるのも、iPS細胞によって患部細胞のモデルを再現できることが大きな要因だろう。しかし、iPS細胞の存在によって解明できた事実が増えるほどに、研究者が着手しなければならない項目は増えていくようだ。井上教授は「少しずつかもしれませんが、前に進めていければと思います」とほほ笑む。
iPS細胞活用による実用化、20年後には実現多数?
井上教授は今後、ALSと同様に、アルツハイマー病に関しても実用化へと進めることができればと考えている。それに加え、難病を根本的に治すためには新技術の必要性も感じているという。
「現在の薬による治療は、悪い部分を取り除いたり、悪影響となるものをブロックしたりする考え方で行われているのですが、それだといったん低下した機能を回復することは難しいかもしれません。そこで将来的に完全な治癒を目指す上では、機能レベルを元に戻す技術も有用であると考えています」

-
京都大学iPS細胞研究所内は、研究者同士のコミュニケーションが図りやすいオープンラボが採用されている
画像提供:京都大学iPS細胞研究所
iPS細胞によるものなのか、はたまた全く新しい技術なのか、もちろん“機能再生”についてはまだアイデアベースであり、何年後に実現とは言えない状況。しかしiPS細胞がそうであったように、ブレイクスルーは階段状にやってくるもの。井上教授は常に希望を持って研究に取り組んでいると言う。
「今は実現不可能に思えても、ずっと目の前の基礎研究を積み重ねて、少しずつかもしれませんが前に進めていくしかありません。そしてALSやアルツハイマー病など難病の薬が、当たり前に使われるようになることを目指します」

-
「難病を根治できる日がやってくるのは近い将来か、遠い未来か、誰にも予想がつかないですが、希望を持っています」と話す井上教授
実際に、iPS細胞から発した治療法や新薬は、実用化を視界に捉えるところまで歩みを進めている。2014年にはiPS細胞から作製した網膜の細胞を移植する臨床研究が、2017年には骨にまつわる難病「進行性骨化性線維異形成症」の候補薬の臨床試験が、2018年8月にはiPS細胞から作った神経細胞をパーキンソン病患者の脳内に移植する世界初の臨床試験が、それぞれ開始されているという。
10年後、20年後には、iPS細胞の活用はさらにさまざまな分野に進出し、細胞組織移植の事例や新薬の実用化が増えていくと井上教授は見ている。
「難病の研究は根治ができるようになれば終わります。その時は今のお仕事が無くなることになりますが、その時が来るように仲間と共に努力させていただければと思います」

-
この記事が気に入ったら
いいね!しよう -
Twitterでフォローしよう
Follow @emira_edit
text:伊佐治龍 photo:中島克樹